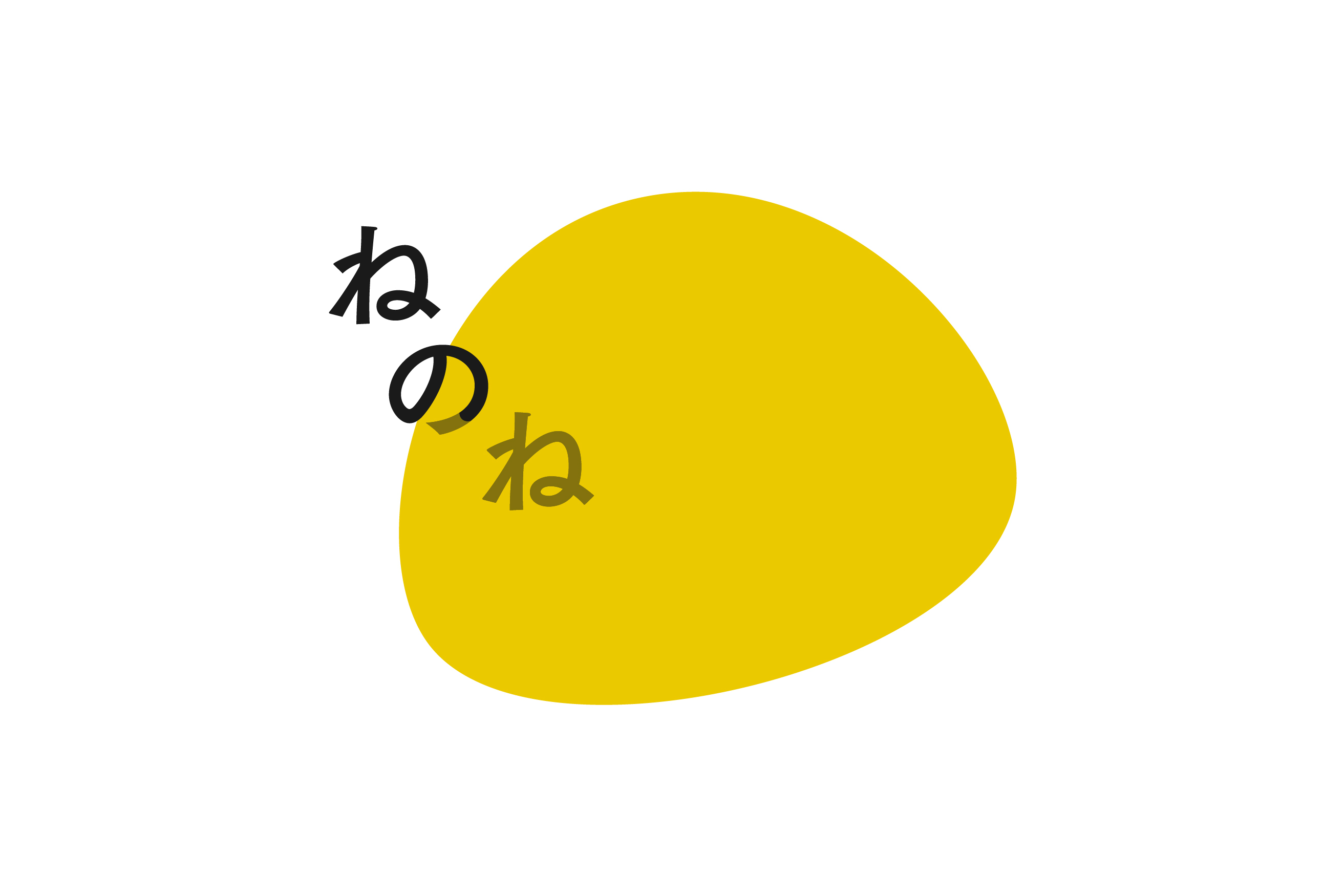- 3
WALDEINSAMKEIT 都市に小さな地球をつくる試み
本プロジェクトは、都市の中に「小さな地球」をつくり、人が地球と直接触れ合う体験を通して、思考の柔軟さや寛容さがどのように立ち上がるのかを探究する取り組みである。
プロジェクト名である WALDEINSAMKEIT(ヴァルト・アインザムカイト) は、ドイツ語で「森の中でひとりでいるときに感じる静けさや、孤独でありながら満たされている状態」を指す言葉である。
それは単なる寂しさではなく、他者や社会的役割から一度距離を取り、自然や世界との関係性の中で自分自身と向き合う感覚を含んでいる。本プロジェクトでは、この WALDEINSAMKEIT 的な状態を、森ではなく都市の中で、地球との接触を通して立ち上げることを試みる。
現代社会は、効率や正解を重視するあまり、他者や環境に対する寛容さが失われつつあるように感じられる。教育の現場に身を置く中で、その傾向は子どもだけでなく、大人自身の中にも強く存在していると実感してきた。
本プロジェクトでは、そうした「こうあるべき」という思考から一度距離を取り、人が地球と触れ直す場をつくることを目指す。
ここで言う「地球」とは、壮大な自然環境そのものではなく、土・水・葉・音といった、ごく身近で、しかし人の思い通りにはならない存在である。
都市の一角に設ける「小さな地球」では、明確な遊び方や正解は用意しない。
ただ触れる、動かす、壊す、何もしない──
そうした行為の中で生まれる感覚や違和感を、必要に応じて言葉にし、共有する場をつくる。
現時点では、「都市に小さな地球をつくる」ための具体的な条件として、次のような体験を想定している。
ひとつは、土の上を歩き、足跡を残すことである。
整えられた地面ではなく、ただ土があるだけの場所に足を踏み入れることで、「歩く」という行為そのものが環境に痕跡を残すことを身体で感じる。
次に、土の上に水を流すこと。
バケツや柄杓などを使って水を流すことで、土が削れたり、水が溜まったりと、元には戻らない変化が生まれる。その変化を評価したり修正したりすることはせず、そのまま次の人へ引き継ぐ。
また、落ち葉に触れること。
積む、分ける、混ぜる、並べる、崩すなど、目的や正解を設定せず、自然物と関わる行為そのものを許容する。意味づけや作品化は求めない。
さらに、目を閉じ、耳を澄ませること。
何かを「する」だけでなく、あえて何もしない時間を持ち、風や足音、水音、周囲の気配に身体を委ねることも、この場での関わり方の一つとする。
これらの体験では、環境を元の状態に戻すことを前提としない。
誰かの行為によって生じた変化や痕跡は、そのまま次の人の「条件」となり、時間の経過とともに場そのものが変化していく。その変化を管理・統制するのではなく、引き受けること自体を探究の対象とする。
また、体験のあとには、感じたことや気づきを、無理のない形で言葉にして残すことを想定している。
それは、完成された感想や意味づけである必要はなく、「気になった」「違和感があった」「よく分からなかった」といった断片的な言葉でもよい。
そうして残された言葉は、匿名のメモや記録として場に蓄積され、次に訪れた人が自由に目にし、触れることができる状態にする。
直接的な対話を強制するのではなく、他者の感じたことや気づきと、時間差で出会うことで、自己対話や新たな問いが静かに立ち上がることを期待している。
行為の痕跡と、言葉の痕跡が重なり合いながら積み重なっていくことで、この「小さな地球」自体が、人と地球との関係性の記録となっていく。
また、このプロジェクトには、提案者自身の自戒も含まれている。
教育の場に身を置いているからこそ、「こうあるべき」「この経験はこう意味づけられるべきだ」という思考に、無自覚に縛られてしまう瞬間がある。
子どもに「寛容さを大切にしてほしい」「子どもに寛容でありたい」と願いながら、その寛容さ自体を管理し、方向づけてしまっているのではないか──そんな違和感を抱いてきた。
本プロジェクトで意図的に「正解」「目的」「意味づけ」を手放すのは、その反省からでもある。
人の側の思考を柔らかくするために、まず人が「地球」と触れ直す必要があるのではないか。
制御できないもの、思い通りにならないもの、変化してしまうものに触れることで、「こうあるべき」という思考そのものが、少しずつ揺らいでいく。
寛容さは、教え込むものではなく、身体を通した経験の中で育つのではないか。
その仮説を、子どもだけでなく大人自身も含めて検証することが、この取り組みのもう一つの探究である。
参加者は、特定の年齢や立場に限定しない。
教育は学校や家庭だけのものではなく、社会全体で担われるものだと考えている。子どもがいるかどうか、教育に関わっているかどうかに関係なく、誰もがこの場に関わることで、「寛容さ」の感覚を検証することを目指す。
この取り組みは、将来的なプレーパークの実装や、学校教育では扱いきれない「試してみる学び」へとつながる入口として位置づけている。
小規模でありながら、都市の中に地球との関係を問い直す余白をつくり、そこから次の実践や場へと接続していくことを目指す。
プロジェクト名である WALDEINSAMKEIT(ヴァルト・アインザムカイト) は、ドイツ語で「森の中でひとりでいるときに感じる静けさや、孤独でありながら満たされている状態」を指す言葉である。
それは単なる寂しさではなく、他者や社会的役割から一度距離を取り、自然や世界との関係性の中で自分自身と向き合う感覚を含んでいる。本プロジェクトでは、この WALDEINSAMKEIT 的な状態を、森ではなく都市の中で、地球との接触を通して立ち上げることを試みる。
現代社会は、効率や正解を重視するあまり、他者や環境に対する寛容さが失われつつあるように感じられる。教育の現場に身を置く中で、その傾向は子どもだけでなく、大人自身の中にも強く存在していると実感してきた。
本プロジェクトでは、そうした「こうあるべき」という思考から一度距離を取り、人が地球と触れ直す場をつくることを目指す。
ここで言う「地球」とは、壮大な自然環境そのものではなく、土・水・葉・音といった、ごく身近で、しかし人の思い通りにはならない存在である。
都市の一角に設ける「小さな地球」では、明確な遊び方や正解は用意しない。
ただ触れる、動かす、壊す、何もしない──
そうした行為の中で生まれる感覚や違和感を、必要に応じて言葉にし、共有する場をつくる。
現時点では、「都市に小さな地球をつくる」ための具体的な条件として、次のような体験を想定している。
ひとつは、土の上を歩き、足跡を残すことである。
整えられた地面ではなく、ただ土があるだけの場所に足を踏み入れることで、「歩く」という行為そのものが環境に痕跡を残すことを身体で感じる。
次に、土の上に水を流すこと。
バケツや柄杓などを使って水を流すことで、土が削れたり、水が溜まったりと、元には戻らない変化が生まれる。その変化を評価したり修正したりすることはせず、そのまま次の人へ引き継ぐ。
また、落ち葉に触れること。
積む、分ける、混ぜる、並べる、崩すなど、目的や正解を設定せず、自然物と関わる行為そのものを許容する。意味づけや作品化は求めない。
さらに、目を閉じ、耳を澄ませること。
何かを「する」だけでなく、あえて何もしない時間を持ち、風や足音、水音、周囲の気配に身体を委ねることも、この場での関わり方の一つとする。
これらの体験では、環境を元の状態に戻すことを前提としない。
誰かの行為によって生じた変化や痕跡は、そのまま次の人の「条件」となり、時間の経過とともに場そのものが変化していく。その変化を管理・統制するのではなく、引き受けること自体を探究の対象とする。
また、体験のあとには、感じたことや気づきを、無理のない形で言葉にして残すことを想定している。
それは、完成された感想や意味づけである必要はなく、「気になった」「違和感があった」「よく分からなかった」といった断片的な言葉でもよい。
そうして残された言葉は、匿名のメモや記録として場に蓄積され、次に訪れた人が自由に目にし、触れることができる状態にする。
直接的な対話を強制するのではなく、他者の感じたことや気づきと、時間差で出会うことで、自己対話や新たな問いが静かに立ち上がることを期待している。
行為の痕跡と、言葉の痕跡が重なり合いながら積み重なっていくことで、この「小さな地球」自体が、人と地球との関係性の記録となっていく。
また、このプロジェクトには、提案者自身の自戒も含まれている。
教育の場に身を置いているからこそ、「こうあるべき」「この経験はこう意味づけられるべきだ」という思考に、無自覚に縛られてしまう瞬間がある。
子どもに「寛容さを大切にしてほしい」「子どもに寛容でありたい」と願いながら、その寛容さ自体を管理し、方向づけてしまっているのではないか──そんな違和感を抱いてきた。
本プロジェクトで意図的に「正解」「目的」「意味づけ」を手放すのは、その反省からでもある。
人の側の思考を柔らかくするために、まず人が「地球」と触れ直す必要があるのではないか。
制御できないもの、思い通りにならないもの、変化してしまうものに触れることで、「こうあるべき」という思考そのものが、少しずつ揺らいでいく。
寛容さは、教え込むものではなく、身体を通した経験の中で育つのではないか。
その仮説を、子どもだけでなく大人自身も含めて検証することが、この取り組みのもう一つの探究である。
参加者は、特定の年齢や立場に限定しない。
教育は学校や家庭だけのものではなく、社会全体で担われるものだと考えている。子どもがいるかどうか、教育に関わっているかどうかに関係なく、誰もがこの場に関わることで、「寛容さ」の感覚を検証することを目指す。
この取り組みは、将来的なプレーパークの実装や、学校教育では扱いきれない「試してみる学び」へとつながる入口として位置づけている。
小規模でありながら、都市の中に地球との関係を問い直す余白をつくり、そこから次の実践や場へと接続していくことを目指す。