NEWVIEW AWARDS 2024 結果発表
3次元空間での新たなクリエイティブ表現と体験のデザインを開拓するプロジェクト/コミュニティNEWVIEWは、空間コンピューティングの可能性を拡張するべく、グローバル・クリエイティヴ・アワード「NEWVIEW AWARDS 2024」を開催しました。
2018年より、過去5回、XR(VR/AR/MR)領域を牽引する次世代アーティスト/クリエイターを発掘・輩出してきたNEWVIEW AWARDS。第6弾となる今回フォーカスするのは、空間コンピューティングがもたらす現実世界の情報・空間・体験のリフレーミングと脱構築、そこから紡ぐ、新たな認知と変容するわたしたちの物語です。
Apple Vision Proのコンテンツを募るSpatial Computing部門、場所性を活かしたAR作品を募るSite-specific AR部門の2部門を設けて実施した今回は、2024年8月21日から2024年10月16日までの募集期間中に、10ヶ国95作品(Spatial Computing:52作品、AR:43作品)の応募があり、事務局による審査を経て19作品(Spatial Computing:11作品、AR:8作品)がファイナリストとして選出されました。
本ページでは、受賞作品の発表を行なっております。
受賞作品の詳細や、惜しくも受賞を逃したファイナリスト作品は、NEWVIEW AWARDS 2024 WEBサイトよりご覧いただけます。
GOLD Prize
Spatial Computing 部門
RESORACLE ─ Heartbeat Verification System ─
Megumu Hanayama

審査員コメント:宇川直宏
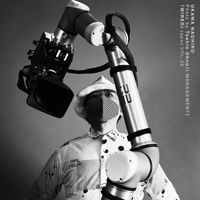
ハウスミュージックの基本は120BPM前後である。このBPMは120が頻脈とされる心拍に由来している。つまり心拍と共鳴しあってダンスフロアの波動は脈打っているのである。この作品「RESORACLE」は「共鳴/想起」を意味する"Resonance"と「神託/啓示」を意味する”Oracle"の造語であるが、このメタフィジカルな作品は、マッシヴデータフロー時代における極めて本質的なデータマイニングを導き出している。"存在の結晶"としての心音は、個人情報が保護される現代において、脳波と共に新しい身体紋理となるであろう。極めて2024年的なビッグデータにおける問題意識と可能性を世に放った作品である。
審査員コメント:KEIKEN

「RESORACLE ─ Heartbeat Verification System ─」は、テクノロジーを通じた繋がりを探求する魅力的な試みであり、私たちの存在の中で最も力強く、かつ人間らしい側面である「心」を中心に据えています。心は、物理的な領域と感情的な領域を繋ぐ強力な架け橋であり、生命を維持するだけでなく、感情を調整し、認知に影響を与え、その生物学的、エネルギー的、そして象徴的な意味合いを通して深い人間的な繋がりを育んでいます。
デジタル空間が日常生活にますます溶け込んでいく現代において、鼓動を存在の印として、脈動する「RESONITE」粒子として視覚化する試みは、詩的でありながらも深遠で、デジタルな存在をより実感できるものにしています。この作品は、仮想空間における体現された存在感に対して独自の視点を提供し、テクノロジーを現実的で生物学的、そして人間的なものに根ざせるようにしています。仮想空間であっても、私たちの存在はただ視認されるだけでなく、感じ取られるものであるということを思い出させてくれます。
私は、テクノロジーやデジタル空間において、より「心」を中心としたアプローチが広まることを心から願っています!
審査員コメント:サエボーグ

人間の最初の記憶は母親の鼓動の音なのかもしれない。 ネコをモフって顔をうずめるときにも、生き物の存在を確認するときに否応なく感じるエンジン音。 この心臓という楽器のような臓器。人生において原初的な体験でもあり、欠かせない臓器の音をコミュニケーションのツールにして生のリズムを確認し合う。 生命というものを定義するときに身体から発せられる音に注目をするという以上に、存在としての鼓動そのものを問うているところを面白く感じた。
審査員コメント:David OReilly

RESORACLEは、デジタル空間における存在のあり方を探求する作品であり、技術の進化やオンラインにおける人の存在の変容に応えてます。人間らしいシグナルである心拍を用いることで、デジタルと現実の境界が曖昧になる世界の中で、自身の身体的な存在を詩的かつ個人的な方法で再確認する機会を提供しています。ソフトウェアやプレゼンテーションの細部にまでこだわりが感じられ、作品としての完成度が高く、非常に魅力的な仕上がりとなっています。
審査員コメント:Gerfried Stocker

Resoracleは、XRの持つ社会的な可能性を深く掘り下げ、このアワードにおいて際立った貢献を果たしている作品です。インタラクティブな拡張現実がますます没入感を増していく中で、私たちの自己像や自己体験がどのように変容していくのかという本質的な問いを投げかけています。これは単なる技術的な発展の話題にとどまらず、芸術的な考察や内省においても極めて重要なテーマです。
さらに、本作は空間コンピューティングの活用領域全体を見渡し、今後この新たな技術がどのように進化していくのかを考察する機会を提供しています。芸術表現のためのツールや舞台として、そしてコミュニケーションの可能性を拡張する手段として、XRが持つ多様な方向性を示唆しているのです。 その意味で、本作はアワード受賞にふさわしいだけでなく、アーティステック・リサーチが成し得ることの力強い証明でもあります。
Site-specific AR 部門
Immersive Novel
カミエナ

審査員コメント:宇川直宏
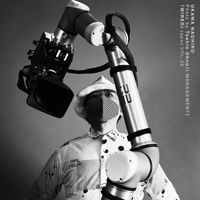
サイトスペシフィックは、イマーシヴと同じく、20年代のマジックワードとして世に機能している。そのような場所の持つ唯一性を考えると、渋谷におけるハチ公前は、歴史と伝統を持った最も普遍的な公共空間であると捉えることができよう。そんなパブリックな「環境に宿る物語」を「体験できる小説」に置き換えたのがこの作品である。渋谷スクランブル交差点奥でのハチ公の霊との対話は拡張現実を超え、人の心の中に形を変えて潜入し、インタラクティヴな"口寄せ”へと変転する。「Immersive Nove」によって、イタコや巫女が霊媒となることと同様、都市というメディアに寄り添う、身体というメタ・メディアの拡張を入れ子体験することになるだろう。
審査員コメント:サエボーグ

この名もなき犬はハチの地縛霊であり、残留思念であり、ゴースト。サイトスペシフィックというテーマに、その土地に縛られた霊を出して登場させるというアイディアはこれ以上ないくらいにサイトスペシフィック。普段は不可視な存在である霊と出会うというのも、テクノロジーの使い方としてもユニーク。交流の後にハチが成仏するというのも、非常にインタラクティブであり、土地の臨場感が強固に作用する、通常の小説ではできない体験。そして自分の心もなぜか浄化される。
こう思うと、ハチ公前を待ち合わせ場所にするという行為は、会いたい人にやっと会えるという、非常にエモい特別な意味と体験をもつということに気付かされる。
人間中心主義の世界において、人間以外の視点をもつことが動物に拡張され、更に不可視な霊の存在にまで意識が拡張されるという、挑戦的な作品だと思う。
審査員コメント:Lu Yang

この作品は愛と感情に満ちており、ARによる表現が非常に適しています。拡張現実を通じて、まるで人々が霊的な世界を見るための目を与えられたかのように、忠実な秋田犬・ハチ公がかつて主人を待ち続けたその場所に浮かぶ姿を目の当たりにすることができ、その光景は深く心を打ちます。作品の内容と技術的な実装が見事に融合しており、非常に完成度の高い作品です。
審査員コメント:David OReilly

Immersive Novelは、ストーリーテリングとAR技術を融合させたユニークなサイト固有の体験を提供します。人気キャラクターを使用してプレイヤーを物語に導くことで、プレイヤー、環境、そしてストーリーとのつながりを生み出します。プレイヤーの動きと展開する物語の相互作用はシームレスで、体験をその場所との生き生きとした記憶に残るインタラクションに変えます。このプロジェクトの魅力は、キャラクター主導のエンゲージメントを用いてAR/VRストーリーテリングの新しいニッチを確立し、持続的な印象を残す能力にあります。没入型ストーリーテリングへの思慮深く創造的なアプローチです。
審査員コメント:Gerfried Stocker

「Immersive Novel」は、クラシックな物語のあらゆる要素を、シームレスにインタラクティブなバーチャル体験の世界へと移し替えるXRプロジェクトです。特に印象的なのは、ロケーション、ナラティブ(物語)、そしてユーザーとのインタラクションが切っても切り離せず一体となっている点です。
その結果、この作品は詩的で芸術性に溢れるだけでなく、芸術とテクノロジーの探求における模範例として、強い示唆力を持つ作品となっています。計り知れないインスピレーションを与えてくれる、受賞にふさわしいプロジェクトです。
審査員コメント:KEIKEN

「Immersive Novel」は、渋谷駅を舞台に、忠犬ハチ公の伝承を中心に構築された、サイトスペシフィックなARの魅力的で思慮深い活用例です。ARは幽霊の表現に特に適しており、私たち自身の目では捉えられないものを明らかにするレンズの役割を果たします。ARを通して幽霊が現れる様子は、霊が私たちの知覚のすぐ外側に存在しているかのように映し出され、体験を一層没入感のあるものにしています。ARが民間伝承や物語を生き生きと伝える、美しい例と言えるでしょう。
SPECIAL PRIZE
TOKYU Corporation PRIZE
Karma
Shinya Hasebe

審査員コメント:David OReilly

この作品は、消えゆく十三のネオンライトのノスタルジアと、環境に深く調和した同期アニメーションを調和させています。アニメーションは壁画に命を吹き込み、過去と現在をつなぎ、慎重に選ばれた音楽が体験を大いに高めています。ファラオ・サンダースへのオマージュは深く響き、ジャズの魂と変革期にあるコミュニティの精神を捉えた音と映像のタペストリーを創り出しています。これは感動的で美しく完成された作品であり、場所、記憶、希望を真に祝福するものです。
審査員コメント:渡邊 彰浩(TOKYU Corporation PRIZE審査員)

素晴らしい作品が沢山あり難しい審査でしたが、その中でもまちづくり活動を生業とする東急株式会社として、「その空間の価値を最も高めるもの」という観点からShinya Hasebeさんの"Karma"を選ばせていただきました。コロナによって生まれてしまったディストピア的空間が、クリエイターやアーティストの力によって、ユートピアへと生まれ変わる…一連のプロジェクトの美しさに大きな感動を覚えました。(また"Karma"をキッカケに、十三という街、淀壁プロジェクト、ファラオ・サンダースについてリサーチを重ねてしまいました)
この作品はフィジカルな壁面アートとのコラボレーションでしたが、都市空間にはたくさんのコラボレーションできる媒介物があることを改めて実感しました。今後も、素敵なコラボレーションが生まれてくることを楽しみにしております。
PARCO PRIZE
Bloom in Motion
JACKSON kaki

審査員コメント:サエボーグ

実際に操作してみると、電脳生け花のようで非常にプレイフルで楽しめた。ガムのように伸び縮みするマテリアルを操る独特の感触も魅力的。
領域の限界を逆手にとったような、木を中心とした区切られた領域で遊べる安心感がここにはある。花以外の恐竜や色んな生き物も登場するところが、小さな空間でありながらも何か新しいワールドを作れるような遊び心地。
その点において、花さかじいさんというよりも、北欧神話の世界樹を連想する箱庭的な遊びのように感じた。
審査員コメント:手塚 千尋(PARCO PRIZE審査員)

デジタルアートならではの「操作する」という体験も含めた作品化、そしてAppleVisionProというデバイスの登場によって、表示されるオブジェクトに、本当にそこにあるかのようなリアリティがもたらされ、さらにハンドトラッキングが可能にする”手でつまむ”行為を通じた「操作」の確かな手応えを得る。最新の技術が可能にする体験と表現をかけ合わせ、かつこの技術の黎明期にふさわしい、次代のリアリティを模索する挑戦的な姿勢を感じる、”今”だからこそ生まれた作品であると言う点が、この作品の大きな価値だと考えました。
そしてこの表現には、バーチャル空間上でつまむという行為がビジュアルだけでなく音楽へ作用されるという体験を通して、新しい芸術表現のひとつになる可能性を感じました。
ASAHI BREWERIES PRIZE
VEGA: Reach your Stars!
grace park

審査員コメント:梶浦 瑞穂(ASAHI BREWERIES PRIZE審査員)

「VEGA」は、インターネットの未来を再定義する意欲的な試みでした。従来の平面的
なスクリーンではなく、3D情報とのインタラクションはよりアイテムの意味性を感じさせられる新しい体験であるとともに、XRの未来をより期待させるものでした。一つ一つの3Dガジェットが丁寧に作られており、クリエイターのK-POPガールグループへの愛情とそれをユーザーにも感じて欲しいという思いを感じました。VEGAの提供する検索エンジンの可視化によるデジタル空間とリアルの境界を超えた情報探索体験は、アサヒビールのビジョンである「すべてのお客様に、最高の明日を」にも通じると感じました。
この革新的なアプローチが、今後さらに多様な分野へと広がり、新たなコラボレーションが生まれることを期待し、アサヒビール Prize に選出致しました。
AWE PRIZE
RESORACLE ─ Heartbeat Verification System ─
Megumu Hanayama

審査員コメント:AWE(AWE PRIZE審査員)

これは、仮想体験の中心に人間を置いた新しいアイデアです。AIの台頭により、ユーザーが本物の人間とやり取りしているという事実に対する信頼は、没入型体験においてますます重要な問いになるでしょう。 バーチャルリアリティーとミクスドリアリティーの技術は、デジタル上で人々をつなげる強力な手段を提供しますが、AIによるアバターや仮想人間が登場することで、ユーザーは相手が本当に人間とやりとりしているのかを判断することが難しくなっています。RESORACLEは、最先端のXR技術と人間の生物学的な基本的要素である心拍を組み合わせたソリューションを提供します。 また、テクノロジーが急速に進化する中で、AIと共存する未来において、どのように自分たちの人間性を確認するのかという問いも提起しています。これは、ほぼ避けられない現実のように思えます。
SPECIAL RECOMMENDATION PRIZE
自己他殺
ノガミカツキ
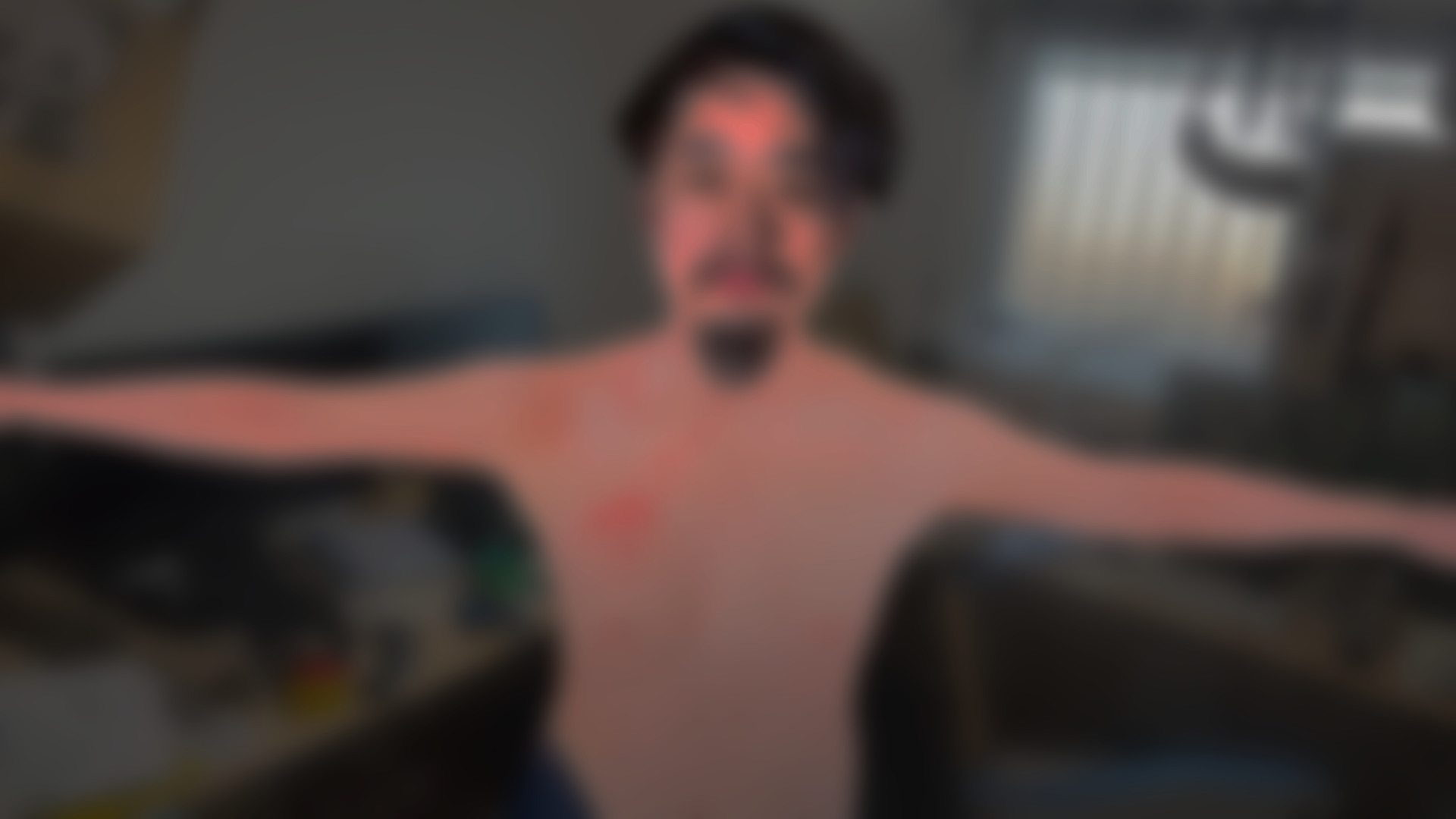
審査員コメント:宇川直宏
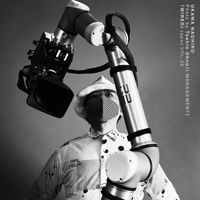
ノガミカツキの作品は、2015年の文化庁メディア芸術祭で新人賞を受賞したgroup_inou のミュージッククリップ「EYE」(橋本麦との共作)の時代から、かれこれ10年に渡って時系列で観てきた。そして去年発表した「Body Memory」では、僕自身がメンターとして彼のプロジェクトと半年間並走し、その純文学のような繊細さとイノセンスに心が震えた。これまで彼の作品には、一貫したアーティストアイデンティティがあった。そう、そこにはアバターをとりまく社会批評性があり、同時にそのことに対しての自己嫌悪が二律背反的に同居している、と、感じていた。そしてそのナイーブさこそが、メディアアートやクロスリアリティのカテゴリーを逸脱し、またテクノロジーそのものに回収されることも毛頭ない純粋芸術としての強度を作品に宿していた。
今回の「自己他殺」もその一貫したコンセプトと地続きだ。この作品の制作動機にはオンラインゲームとSNS、そのヴァーチャルとセミ・リアルな時空の中で日夜行われている観念的な他殺、また一方で、先進国で最も自殺率が高い日本についての批評性がある。故にここで扱う「死」はセンシティブな内容ではあるが、自殺や自傷行為を助長したり扇動したりする表現ではない。むしろこの作品で体験したヴァーチャルな「自己他殺」によって、自殺を踏みとどまった人が現れてもおかしくないだろう。それぐらい明確な問題提起をこの作品は打ち出している。
そういえば90年代にミリオンセラーとなり社会現象を巻き起こした鶴見済の著書『完全自殺マニュアル』は「いつでも自殺できることを心の支えに、世の中を生き延びる方法を逆説的に説いた」名著であったが、当時は様々な自殺現場でこの書籍が発見され、賛否両論を巻き起こした。しかし、インターネット以降の現代においては、『完全自殺マニュアル』をお守りにして生き続けている人々のブックレビューがサイバースペースに溢れている。つまり、諸刃の剣なのだ。
諸刃の剣であるからこそ、この作品「自己他殺」の概要を示すYoutubeムービーにも警告が出る。これは当然のことだ。捉え方は千差万別、しかし此処には死がまとわりついているからである。簡潔に言うとビューワーの抱える希死念慮(散発的に出現する死についての願望)や、自殺への衝動に接続する懸念がある為だ。よって"こころの健康相談統一ダイヤル"の電話番号が作品概要ムービーに自動的に紐付いて表示され続ける。なぜならこのムービーのタイトルに"自殺"という言葉が組み込まれているからである。Youtubeでは"自殺"というワードで検索すると「ひとりで悩まないで」と表示され「それでも表示する」というボタンを押すとやっと動画が立ち現れる。つまりこの作品も例外ではなく、他者と共有することが大変デリケートな作品であることは間違いない。したがって現代においてはアクセスには幾十もの説明とセキュリティを通過させた上で、ようやく体験することを選択する権利を与える必要がある。そう、「自殺」ではなく、"死の概念の軽視”を問題視し再考を促す「自己他殺」の体験でさえも….。
ゆえに我々はこの作品について長時間に渡って議論した。結果、審査員それぞれがこの作品を独自の視点から評価し、SPECIAL RECOMMENDATION PRIZEを受賞するに至った。改めてノガミカツキの最新作を彼の個人史の一部に組み込もう。この作品の真価は歴史と共に改めて見出されるに違いないのだから。これはノガミカツキが謳うブルースなのである。
審査員コメント:サエボーグ

人間と殆ど見分けがつかないアンドロイドと性的なことをしたり、殺したりできる巨大遊園地を描いた映画「ウエストワールド」を一見連想させられる。しかし、この作品は自分の顔を反映して自分自身を殺すという点で、生まれなおしや、自己再生の儀式ともとれるところが新しい。
実際、自分の本当の死(後)は体験することが出来ないため、人にとって一番重要な死は他者の死になると思う。では、自分の死を他者のように見つめ直してみてはどうか。
バーチャルの世界で簡単に人が殺せる世界において、例えフィクションだとしても、フィクションだからこそ、自分自身を殺すという体験により逆説的に生というものを見つめ直す機会となるのではないか。死の問題以上に、自分の生をどのように捉えるか。暴力的なケアの儀式として作用することを期待する。
審査員コメント:Lu Yang

選考過程でこの作品にほぼ満点を与えましたが、自殺というテーマがネガティブな影響を与える可能性があるとの懸念から、かなりの論争を引き起こしました。私の焦点は、アーティストが自身を仮想の没入型環境で投影しながら、こうした社会問題に立ち向かう勇気にあります。これは確かに観客の共感を高め、社会問題についての反省を促すことができます。私は、アーティストには視覚的に魅力的なイメージを単に提示する以上に、思考を喚起する社会的責任があると信じています。したがって、この作品は公衆に見てもらう必要があると考えています。
審査員コメント:David OReilly

Self-Homicide は、ミックスド・リアリティを通じて自己傷害という衝撃的な行為を突きつける、大胆かつ挑発的な作品です。ソフトウェアの制約を巧みに活かし、強いインパクトを持つ体験を生み出しているものの、その野心的なコンセプトを完全に体現するにはまだ発展の余地があるように感じます。それでも、テクノロジー、アイデンティティ、そして死というテーマに踏み込んだそのアプローチは印象的であり、困難かつ複雑な問いに挑む姿勢には強く惹かれます。さらなる洗練を加えることで、より完成度の高い作品へと昇華できるのではないでしょうか。
審査員コメント:Gerfried Stocker

作品「Self-Homicide」は、その大胆かつ繊細なテーマアプローチにより、従来のXRプロジェクトの枠をはるかに超える驚きをもたらしました。また、この作品は、没入型のインタラクティブな拡張現実が進む時代において、我々の自己認識がどのように進化するのかという本質的な疑問を投げかけています。
仮想世界で「他者」として自分を体験し、「他者」の中に自分自身を見出すという体験は、技術開発にとって非常に魅力的なテーマであると同時に、芸術的探求や内省の根源的かつ普遍的なテーマでもあります。
XRの応用範囲を力強く拡大し、並外れたテーマに挑戦し、要求の高いながらも考えさせられるユーザー体験を提供することで、このプロジェクトは空間コンピューティングにおけるあらゆる可能性を、開かれた心で受け止めることの重要性を私たちに訴えかけています。
これらの理由から、今回のSPECIAL RECOMMENDATION PRIZEにふさわしい受賞作であるだけでなく、芸術的研究がもたらす影響力の強い実例とも言えます。
審査員コメント:KEIKEN

「Self-Homicide」は、日本や世界における高い自殺率という深刻な問題に真正面から向き合い、思考のきっかけとして用いる作品です。インタラクティブなXRと実写映像を融合させることで、参加者に自身の死と向き合うことを強く迫ります。本作は、デジタル空間における死への感覚の麻痺に疑問を投げかけ、自殺というテーマを新たな視点で捉え直すことで、認識の大きな転換を促す可能性を秘めています。自らを客観的に見ることで、アイデンティティや自己のコントロール、そしてテクノロジーが自己認識に与える影響について考えざるを得ません。緊急性の高いテーマに果敢に挑んだ、刺激的かつ思索を促す作品です。

